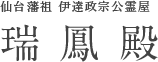令和七年度 伊達忠宗公368遠忌法要「藩主墓室の蓋石と板石塔婆」ー地元産の石が支える御霊屋(三)ー
2025.07.31
仙台藩二代藩主伊達忠宗公は、1658年7月12日、仙台城にて60年の生涯を閉じました。翌年の5月には三代藩主綱宗公より御霊屋建立が命じられますが、綱宗公の強制隠居により造営が遅れ、御霊屋感仙殿は1664年に完成しました。感仙殿は瑞鳳殿と同様に絢爛豪華な一構の建築物で、後年国宝に指定されましたが、戦災によって木造部分はすべて焼失しました。残されたのは地中にあった墓室や板石塔婆、石段、石垣、石畳などの石造物や錺金具などの金工品のみです。
本栞では政宗公、綱宗公の遠忌法要ブログに引き続き、瑞鳳殿境内地内に使用された石材についてご紹介いたします。
〇忠宗公墓室蓋石 板碑の石材「井内石」
感仙殿の地下、忠宗公が副葬品と共に埋葬されていた石室には、蓋石として三滝玄武岩と井内石(稲井石)の板碑が用いられていました。井内石は現在の石巻市稲井地区で切出された「仙台石」とも称される石材で、CaOが10%程度含まれる事から、細かい刻字等の加工がし易いという特徴があります。また、厚く板状に割れ(スレート劈開性)、表面は美しく整い、磨くと深い灰色の艶を呈すため、古くから石碑や板碑などに用いられて来ました。忠宗公墓室蓋石の井内石も、中世(14世紀)に造られた板碑の再利用であり、宗教上の聖地でもあった経ヶ峯に建てられていたものをそのまま流用したものと考えられます。
忠宗公の墓壙から出土した板碑は5枚で、いずれも2mを超える大きさのものであり、蓋石として利用する際には再加工が加えられたものもあります。板碑は亡者となった人物の菩提を弔うために造られたものですが、うち2枚は長い間敷石として使用されていたようで、願文や年号は擦り切れて読めません。年号が読み取れるもので最も古いものは1323年の造立となっており、忠宗公の埋葬時からして300年以上前のものです。仙台市内には複数の井内石の板碑や句碑、記念碑があり、古いものでは鎌倉時代建立の板碑が青葉区八幡町澱不動尊や同じく青葉区川内東北大植物園内にあり、当時の信仰の有りかを示す手がかりともなっています。
建造年代と井内石の帯磁率の関係についての研究も進められており、より厳密な産地推定や流通経路についての知見が今後得られることが期待されます。
※帯磁率…石材に含まれる磁性鉱物の量を示す率

忠宗公墓室の蓋石となっていた板碑
〇板石塔婆の石材「丸森産花崗岩」
感仙殿の北隣には9代・11代公夫妻の板石塔婆があります。伊達家では4代藩主伊達綱村公の時にそれまでの御霊屋式の墓を排し、石造りの墓標である板石塔婆を地上に建てるようになりました。この板石塔婆は、遠目では分かりませんが、一般的な墓石でもよく使用されている花崗岩(御影石)で造られています。花崗岩は深成岩の一種で有色鉱物の黒雲母や角閃石、石英、斜長石、カリ長石などが含まれ、磨くと美しい光沢が出るため、単なる建材としてだけでなく、意匠材としても利用されています。また圧縮強度が高いため耐火性や耐候性に優れ、長期間風雨にさらされても劣化しにくいという特性があります。産地によって鉱物の含有量が異なっており、色調も白色優位から肌色優位のもの、有色鉱物の含有量が多くなり、カリ長石が少なくなるにしたがって花崗閃緑岩、石英閃緑岩などと名前が変わります。
大正年間出版の『電狸翁夜話』には「肯山公(4代綱村)以後代々藩主の碑石は、伊具郡丸森産の花崗岩を用ひることに定め」たとあり、記述の通りだとすれば、ここ経ヶ峯の9代・11代公夫妻の板石塔婆は、丸森産の花崗岩である事になります。実際、地質図(裏面)を参照すると丸森町南部から西半部にかけて町の多くの部分で花崗岩の分布を確認する事ができます。
2020年に東北大学名誉教授の蟹澤聰史氏が「伊達家無尽灯廟調査会」と共同で、4代綱村公、5代吉村公、12代齊邦公の板石塔婆に含まれる磁性鉱物の量に依存する帯磁率の測定と丸森町で採取された複数の花崗岩石片で同様の測定及び比較を行ったところ後者の数値にばらつきはあるものの、総じてともに低い値を示しました。
また、今回改めて、11代齊義公の板石塔婆(表紙)から剥離した欠片と丸森の瑞雲寺ご住職からご提供いただいた丸森大石破片の帯磁率測定を行った結果、同様に低い数値が検出されました。これにより11代齊義公の板石塔婆が丸森産である可能性が一層高まったと言えます。
先の『電狸翁夜話』ではさらに「同地(丸森)産の花崗岩は「御止山」と称へ妄りに掘出することは勿論、掘出したものも踏石はいふまでもなく、燈籠にすることまでも禁止した」との記述があり、丸森産の花崗岩を藩主墓標の石材として特別視し、独占しようとしていた事が伺えます。
他に宇多郡(福島県新地町)産の花崗岩を墓石に使用したとの説もあり、地質図上でも丸森町と新地町にまたがる鹿狼山北部に花崗岩の分布が見られます。ただし、鹿狼山の花崗岩は丸森花崗岩とは見かけも時代も異なる花崗岩体が広く分布する事から、その他の小規模花崗岩岩体から墓標に足る大きさの石が切出せたかどうかは不明です。
明治39年に名取郡長町の古老により記された『仙台市外神拝記』によると、新地町の花崗岩は、岩沼の玉崎まで舟積みされ、その後は75mにも及ぶ太い2本の麻縄をかけて木車で運ばれたとされます。この一行が町を通行する際には近隣の村などからも人々が集まり、老若男女の区別なく大繩に取り付き共に石を曳いたと言います。墓標となる石材の移送に、民衆が積極的に関わっている様が興味深く感じられます。
令和7年度の法要ブログは御霊屋や墓標に用いられた石材について紹介して参りました。普段顧みられることが少ない石造物ですが、この機会に身近な地元産の石についてもぜひ注目していただければ幸いです。

齊義公墓碑破片を拡大